No.6 丂2003擭9寧18擔
嵅摗丂晀梇丂
実懷揹榖帠嬈幰偺斕攧愴棯
---- 寧師弮憹戜悢偐傜偺悇應 ----傑偊偑偒
傢偑崙偺実懷揹榖偼弴挷偵偦偺戜悢傪怢偽偟偰偒偨偑丄晛媦棪偑60%傪挻偊丄廀梫偺摢懪偪偑 庢傝嵐懣偝傟傞傛偆偵側偭偨丅揹婥捠怣帠嬈幰嫤夛乮TCA乯偑枅寧敪昞偟偰偄傞実懷揹榖宊栺悢 偺僨乕僞偐傜偦偺條憡傪悇應偟偰傒偨丅
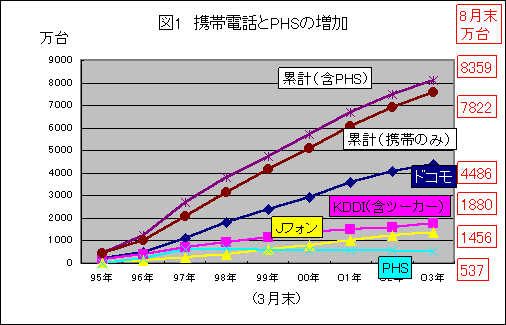
侾丏実懷揹榖偺憹壛
恾1偼夁嫀2擭娫偵偍偗傞実懷揹榖偺憹壛偺柾條傪帠嬈幰暿偵帵偟偨傕偺偱偁傞丅偙傟傑偱偼 枅擭傎傏1000枩戜偢偮憹壛偟偰偒偰偄偨偑丄嵟嬤偱偼傂偲崰偺惃偄偼尒傜傟側偄丅偙偺揰傪 柧妋偵偡傋偔丄夁嫀2擭娫偺枅寧偺弮憹悢傪挷傋偰傒偨丅恾2偼丄慡崙実懷揹榖偺枅寧偺弮憹悢偲儌僶僀儖IP宊栺偺弮憹悢傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅
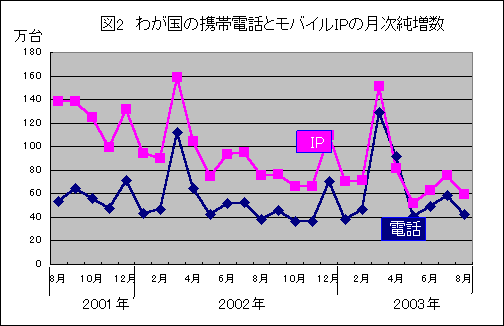 堦尒栚偵晅偔偺偼丄2002擭丄2003擭嫟偵3寧偺憹壛偑挊偟偄偙偲偱偁傞丅偙傟偼丄奺帠嬈幰偑
寛嶼偺悢帤傪忋偘傞偨傔擭搙枛偵寖偟偄斕攧峌惃傪偐偗偰偄傞偙偲偲丄怴擖妛丒擖幮摍偺廀梫
偑懡偄偙偲傪帵偟偰偄傞丅偙偺3寧偺僺乕僋傪彍偗偽枅寧偺憹壛悢偼40悢枩戜偺墶偽偄偱偁傞偲
尵偊傞丅擭枛偵偼偳偺彜昳偵傕尒傜傟傞擭枛廀梫偑尒傜傟偨傕偺偺丄嶐擭偺10寧丄11寧偺弮憹悢
偼偄偢傟傕36枩戜偺僆乕僟乕偱巎忋嵟掅傪婰榐偟偰偄傞丅
堦尒栚偵晅偔偺偼丄2002擭丄2003擭嫟偵3寧偺憹壛偑挊偟偄偙偲偱偁傞丅偙傟偼丄奺帠嬈幰偑
寛嶼偺悢帤傪忋偘傞偨傔擭搙枛偵寖偟偄斕攧峌惃傪偐偗偰偄傞偙偲偲丄怴擖妛丒擖幮摍偺廀梫
偑懡偄偙偲傪帵偟偰偄傞丅偙偺3寧偺僺乕僋傪彍偗偽枅寧偺憹壛悢偼40悢枩戜偺墶偽偄偱偁傞偲
尵偊傞丅擭枛偵偼偳偺彜昳偵傕尒傜傟傞擭枛廀梫偑尒傜傟偨傕偺偺丄嶐擭偺10寧丄11寧偺弮憹悢
偼偄偢傟傕36枩戜偺僆乕僟乕偱巎忋嵟掅傪婰榐偟偰偄傞丅
師偵IP偵偮偄偰偼丄戜悢偺憹壛偲嬌傔偰傛偄憡娭傪帩偭偰偍傝丄偐偮偦偺悢偑尭彮偺堦搑傪 扝偭偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅偙傟偼偙偺2擭娫偵IP婡擻偺偮偄偨怴偟偄揹榖婡偑懡悢弌夞傞傛偆偵 側傞偲嫟偵丄僀儞僞乕僱僢僩傗儊乕儖傊偺娭怱偑崅傑傝丄杦偳偺恖偑IP婡擻晅偒偺揹榖婡傪 峸擖偡傞傛偆偵側偭偨偨傔偱偁傠偆丅
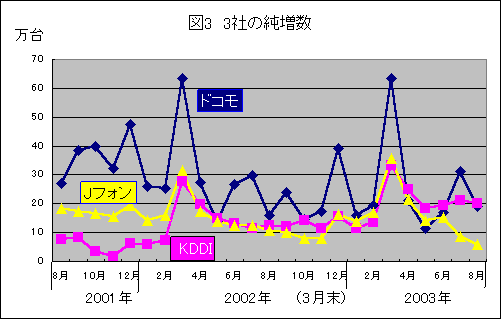
俀丏奺幮暿弮憹悢
乮侾乯奺幮偺斾妑
恾俁偼NTT僪僐儌丄KDDI乮au偺傒丗僣乕僇乕傪彍偔乯丄 J僼僅儞奺幮偺弮憹悢傪斾妑偟偨傕偺偱偁傞丅奺幮偲傕偵俁寧偺弮憹偑嵺棫偭偰偄傞丅 慡懱偺孹岦傪尒傞偲丄僪僐儌偲J僼僅儞偑慟尭偟偰偄傞偺偵懳偟丄KDDI偼柧傜偐偵慟憹丄 偟偐傕偦偺妱崌偑戝偒偄丅恾係偼僪僐儌偺弮憹悢傪PDC偲FOMA偵暘偗偰帵偟偨傕偺偱偁傞丅3寧暲傃偵擭枛偵偍偗傞憹壛 偑挊偟偄丅
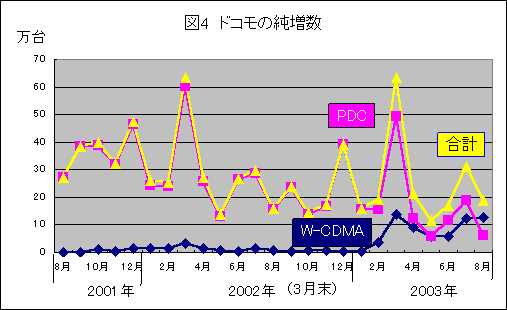
乮俀乯僪僐儌
偟偐偟偙偙2擭娫偱偼弮憹悢偑慟尭偟偰偍傝丄杮擭8寧偵偼2擭慜偺敿悢掱搙傑偱 棊偪偰偄傞丅 傕偆堦偮拲栚偡傋偒偼丄晄怳傪嬌傔偰偄偨FOMA偑丄杮擭3寧偵戝偒偔桇恑偟丄 俆寧枛偵偼PDC偲傎傏摨悢偺憹壛傪帵偟丄俉寧枛偵偼PDC偺俀攞偺憹壛傪婰榐偟偨偙偲偱偁傞 丅FOMA偺弮憹悢偑PDC傪忋夞偭偨偺偼巎忋弶傔偰偱偁傞丅偙傟偼摨幮偑抂枛偺斕攧愴棯傪戝偒偔 揮姺偟丄俁G偺悽奅愴棯傪傕尒悩偊偰FOMA偺斕攧偵廳揰傪抲偒巒傔偨偨傔偲悇應偝傟傞丅
乮俁乯KDDI乮au偺傒丗僣乕僇乕傪彍偔乯
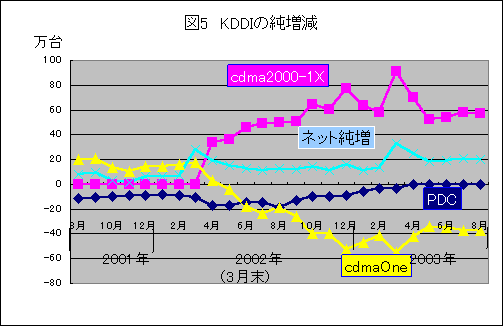 恾俆偵帵偡KDDI偺摦岦偼嬌傔偰僪儔儅僥傿僢僋偱偁傞丅偡側傢偪丄
恾俆偵帵偡KDDI偺摦岦偼嬌傔偰僪儔儅僥傿僢僋偱偁傞丅偡側傢偪丄嘆丂嶐擭3寧傑偱暯扲側怢傃傪帵偟偰偄偨cdmaOne偑丄4寧偐傜cdma2000-1X偵庢偭偰戙傢傜傟丄 摿偵12寧丄3寧偺廀梫婜偵偦傟偑尠挊偵尰傟偰偄傞丅
嘇丂PDC偼枅寧弮尭傪帵偟丄杮擭3寧枛傪傕偭偰僒乕價僗傪掆巭偟偨丅
嘊丂憤崌揑側弮憹悢偼塃尐忋偑傝偱偁傝丄杮擭8寧偵偼2擭慜偺俀乣3攞憹偲側偭偰偄傞丅
乮係乯J僼僅儞
恾俇偼J僼僅儞偺PDC偲W-CDMA偺弮憹傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅摨幮偺3寧偺怢傃偼懠幮偵斾偟挊偟偔 崅偄丅傑偨弮憹悢偼媫懍偵尭彮偺堦搑傪扝傝丄杮擭8寧偵偼丄2擭慜偺3暘偺堦埲壓偲側偭偰偄傞丅 嶐擭枛偐傜巒偭偨W-CDMA偺憹壛偼旝乆偨傞傕偺偱偁傞丅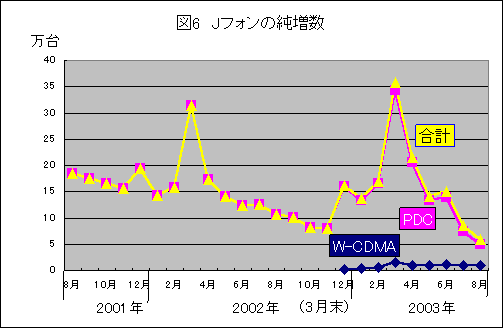
俁丏丂戞俁悽戙実懷揹榖僔僗僥儉乮俁G乯偺弮憹悢
恾俈偵俁幮偺俁G偺弮憹悢傪帵偡丅W-CDMA偲偺斾妑偼摉傪摼側偄偐傕偟傟側偄偑丄 KDDI偺cdma2000-1X偺怢傃偼挊偟偔崅偔丄俉寧枛尰嵼偺椵寁偼973枩傪悢偊傞偵帄偭偰偄傞丅 偙傟偼懡偔偺cdmaOne棙梡幰偑cdma2000-1X偵忔傝姺偊偰偄傞偙偲傪帵偟丄cdma2000-1X偺摫擖偼 戝偒側惉岟傪廂傔偨傛偆偩丅偙偺曽幃偼cdmaOne偵斾傋偰揹榖壛擖幰梕検偑2攞偵側傝丄 僨乕僞偱偼144kbps偺揱憲偑壜擻偱摦夋偺僗儉乕僘側揱憲傕壜擻偱偁傞丅僀儞僼儔偲偟偰偼 廬棃愝旛偺娙扨側夵廋偱偡傒丄梕堈偵慡崙揥奐偑偱偒偨偙偲偑岠壥揑偩偭偨偲峫偊傜傟傞丅
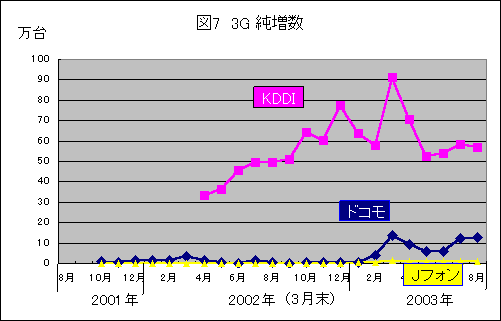 堦曽FOMA偱愭峴偟偨僪僐儌偼丄弶擭搙偺攧忋栚昗傪戝暆偵壓曽廋惓偟偨偑丄忋婰偺傛偆側
斕攧愴棯偺揮姺偵敽偭偰弴挷偵壛擖幰偑憹壛偟偰偍傝丄8寧枛尰嵼偱偼椵寁79枩戜庛偲側偭偰偄傞丅
棫愳幮挿偼愭廡乽80枩戜傪撍攋偟丄斕攧栚昗乮150枩乯偼払惉壜擻偩乿偲嫮婥偺敪尵傪偟偰偄傞丅
僪僐儌偼儓乕儘僢僷偱偺i儌乕僪偺晛媦偵椡傪擖傟傞偲摨帪偵丄暷崙AT&T儚僀儎儗僗偵俁G偺媄弍丒
帒嬥偺墖彆傪峴偭偰偍傝丄崱屻偺忬嫷偑拲栚偝傟傞丅
堦曽FOMA偱愭峴偟偨僪僐儌偼丄弶擭搙偺攧忋栚昗傪戝暆偵壓曽廋惓偟偨偑丄忋婰偺傛偆側
斕攧愴棯偺揮姺偵敽偭偰弴挷偵壛擖幰偑憹壛偟偰偍傝丄8寧枛尰嵼偱偼椵寁79枩戜庛偲側偭偰偄傞丅
棫愳幮挿偼愭廡乽80枩戜傪撍攋偟丄斕攧栚昗乮150枩乯偼払惉壜擻偩乿偲嫮婥偺敪尵傪偟偰偄傞丅
僪僐儌偼儓乕儘僢僷偱偺i儌乕僪偺晛媦偵椡傪擖傟傞偲摨帪偵丄暷崙AT&T儚僀儎儗僗偵俁G偺媄弍丒
帒嬥偺墖彆傪峴偭偰偍傝丄崱屻偺忬嫷偑拲栚偝傟傞丅
J僼僅儞偺W-CDMA偼傑偩愭偑尒偊偰偄側偄偑丄Vodafone偵柤徧曄峏傪峴偆傋偔丄儓乕儘僢僷彅崙
偲偺儘乕儈儞僌傪攧傝暔偵偟偰怹摟傪寁偭偰偄傞偑丄摉柺偼GSM偲偺僨儏傾儖儌乕僪偱偵傛傞
傕偺偲巚傢傟丄儓乕儘僢僷彅崙偱偺W-CDMA偺晛媦傪懸偨側偗傟偽側傜側偄偩傠偆丅